体験談 2025.09.16
体験談vol.22 河周子さん本人<後編>

・患者さんの病名:リウマチ性多発筋痛症、神経因性膀胱ほか
・患者さんの年齢:95歳
・訪問診療を受けている期間:1年11ヶ月
・家族構成:独居。長男さん家族が近隣在住、長女さん家族が外国在住
・インタビューに答えてくださる方:河周子さん(本人)
・インタビューの時期:訪問診療開始から1年11ヶ月後

目次
このお家のことについて教えてください。
この家は息子が大学の建築学科の課題で設計したものです。家の建て替えを考えている時に、息子が大学の先輩に相談したら、「なんで自分が設計士になるのに、自分にやらせてくださいって言わないんだ」と嗾けられたそうです。息子が設計して、先輩に工務店を紹介してもらって、建ちました。家を建てているとき不安でしょうがなくて、新居が倒れる夢を3回くらい見たのですが、これから独り立ちしていく息子を親が信頼しなくてどうするんだと自分に言い聞かせました。この家ももう築44年になります。あちこちガタがきていますが、私が生きている間はもってくれたらと思っています。
息子が設計した家に、夫がいろいろ手を加えています。取手やドアノブなどは凝って作っていました。このオブジェは夫が小学生の夏休みの工作を手伝って作ったものです。当時から子どもの宿題を親が手伝う文化があって、近所の子どもを何人か集めて、一緒に工作をやったんです。段ボールを5mm幅に切ってそれを黒く塗って、好きな形に切って貼って。この界隈の子どもがみんな同じものを作ってきたら先生もわかるでしょうが、周りのお母さんたちからは、河さん助かった、と言われましたよ。
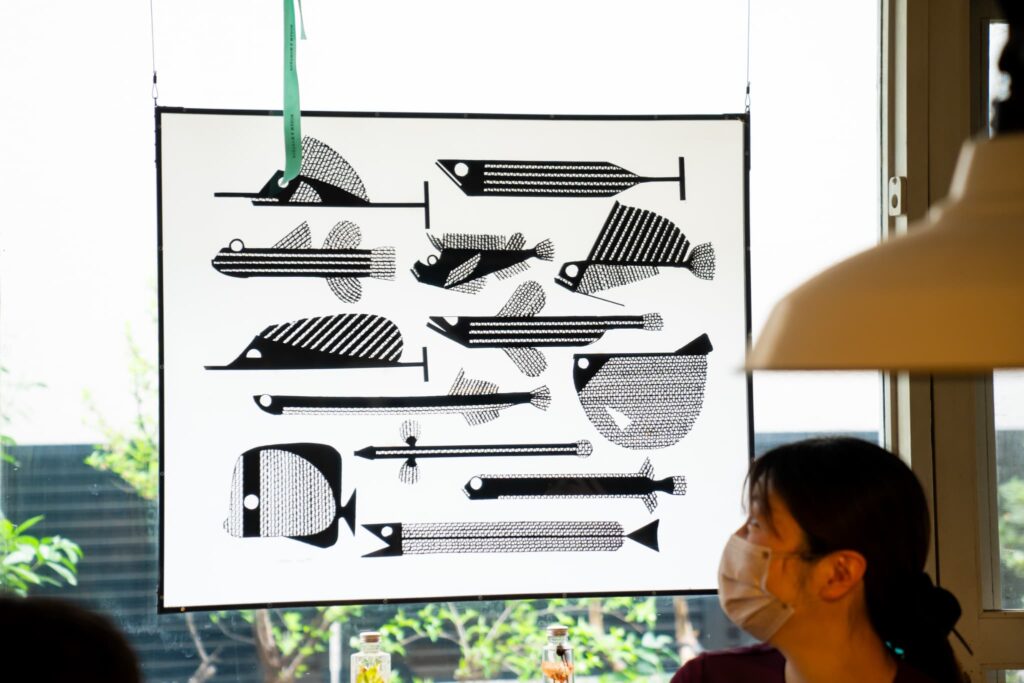
ご主人の最期について教えてください。
夫は94歳で老衰で亡くなりました。体が弱ってくるとせん妄が始まり、戦争中の色々な思い出が蘇って来るようでした。夜中にうろうろ歩いてしまい、私は心配で夫のベッドの隣のソファで寝たら、腰を痛めてしまいました。夫は夜になると目つきが変わってきて、「布団をかけて」「体を起こして」とあれこれ5分おきに要求を繰り返して大変でした。朝起きたら夫がベッドから落ちていたことが3回あって、3回目でもうダメだと思いました。当時私も84歳でしたから、老老介護で思うようにいきませんでした。
最期の1週間は入院してもらいました。入院の際に、延命も治療も希望しませんと医師にお伝えしていたのですが、入院の同意書の中に拘束に関するものが入っていて、私と娘は深く考えもせずにサインしてしまったのです。お見舞いに行った際に、夫が体幹ベルトをされているのを見て愕然としました。夫はなにしろ我の強いひとで、こんなふうに身動きできなくされるのは本当につらいだろうなと、心底思いました。主治医に「意識がある状態で拘束は可哀想だから、眠る薬を使ってもらえませんか」とお願いしたのですが、医師は私が安楽死を希望しているように捉えたのか、「それはできない」と言われました。夜通し考えて、翌日もう一度主治医に、「夫が眠れていないみたいだから、一度眠る薬を飲ませてもらえませんか」とお願いしても了承の返事はもらえませんでした。でも、その翌晩くらいにご臨終ですと連絡が来たので、夫がつらいと感じる時間が長引かなくてよかったと思いました。
10年以上が経過したいまでも、夫の最期の時に拘束をしてしまったということは悔いていて、お墓に入ったら夫に謝らなければいけないなと思っています。
河さんが携わっていた杉並区の社会福祉活動について教えてください。
白川すみ子さんという、後に私の50年来の友人になる方が30代後半の時に、パーキンソン病の実母と脳梗塞後遺症の義父の介護を同時に担うことになり、その経験から「これほど大変な問題を家族という小さな垣根の中に抱え込んでおいていいのだろうか?もっと社会みんなで助け合える方法はないのだろうか」と考えて、一緒に活動するひとを探し始めました。当時の杉並区は他の23区よりも社会福祉の制度が遅れていて、たくさん困っているひとがいたんです。病院で治療したけれど身寄りがなくて行き場がない方だったり、発達障害の子どもを育てる片親の家庭だったり。そういう方たちのために何ができるだろうかと考えて、まずは洗濯をしてあげるひとと、ご飯を作ってあげるひとを白川さんが募集しました。
私はその頃40代で、姑を看取り、一息ついていた時だったのですが、白川さんの話を聞き、避けては通れないものを感じて活動に加わりました。「杉並・老後をよくする会」が発足し、洗濯や料理もしましたし、白川さんと一緒に専門家の話を聞きに行ったり、区長や区議会などいろんなところに交渉しに行ったり、署名活動をしたりしました。
当時は、みんな穏やかで優しいひとばかりでした。決してみんな裕福ではなく、ギリギリのところで生計をたて、子どもを育てていたのだけれど、「家のおかずを1人分多く作ってもっていくことならできるでしょ」と言われたら、食費を出せなんて言わずにやってくれるような、そういう思いやりが当たり前にあったんです。洗濯だって、当時は感染症のことなんて考えもしなかったから、他のひとの家の汚れた下着を持ち帰って、手で洗っていました。しばらくやっていくうちに、新宿区では配食サービスをやっているという情報を新聞で得て、新宿区にどういう制度なのか聞きにいき、杉並区に直談判しました。何度も通い詰めて、材料費だけは区が負担してくれることになり、最初は10食からはじめ、最後には1万食を配る大きな活動になりました。
白川さんの声から始まった活動でしたが、みんな同じような悩みを抱えていたのだと思います。「これじゃあ、私たちが歳をとった時にも誰も看てくれないよね」と、なんとか社会のあり方を変えていかなければと、たくさんのひとが賛同してくれたのです。だんだん会員が増え、専門家も動いてくれるようになりました。
うまくいかなかったこともたくさんありましたが、何十年も諦めずに続けたことを誇りに思っています。私たちの活動は2000年に発足した介護保険制度の源になっています。デイサービスや配食サービスは私たちがやっていたことですし、社会福祉法人を立ち上げて特別養護老人ホームだって作りました。当時は前例がなく時期尚早で作れなかった小規模多機能施設も、いまは全国に複数できています。
「杉並・老後をよくする会」は50年の節目で幕を閉じました。なぜかというと、会員が年をとってきたからです。何をするにも若さというエネルギーは必要で、会員の平均年齢が上がるにつれ、会合を開こうにもだんだんひとが集まらなくなってきたんですね。だから、ボランティアやおしゃべりの会などのグループ活動は続けるけれど、運動体としては解散することにしたんです。解散することに寂しさもありましたが、専門家の先生に「活動を託すために社会福祉法人を作ったんでしょ。あとは任せなさい」と言われ、その通りだと思いました。

河さんはご自身の最期についてはどうお考えですか?
できればこの家にずっといたいとは思っていますが、私にとって下の世話を息子に頼むのだけはどうしても受け入れ難いことなんです。娘は海外にいるから頼れないし、ヘルパーさんだって四六時中一緒にいてもらえる訳じゃないから、どうしたってそばにいる息子に頼まなきゃいけない時が来るかも知れない。そうなるくらいなら、施設に入りたいと思います。
いま私は、ヘルパーさんや療法士さん、看護師さん、ケアマネジャーさん、それから香西先生の手を借りてひとり暮らしをしています。この体制というものはとても素晴らしいもので、ケアマネジャーさんは常に私の半歩先の未来のことを予測して、前もってサービスの調整などを行ってくれているし、何かあったらすぐ看護師さんや香西先生に電話で相談できるし、心配性な私のために置き薬も用意してもらっています。そのおかげで安心して暮らせています。
施設に入るとなると、いまの体制が全部なくなって、一から新しいひととの関係性を築いていかないといけません。郷にいれば郷に従えで、私は新しい環境にも意外と馴染める気はしますが、家で生活できないような状況だと自分で認識するまでは、いまの生活を捨てられないなと思います。ひとり暮らしにこだわっているというより、いまの体制や人間関係がとても貴重なもので、惜しいなと思っているんです。
私が理事をしていた社会福祉法人の特別養護老人ホームは、いまは区が入所を管理しています。入所のシステムは、入居希望者の状態に合わせて点数をつけて、点数の高いひとを優先的に入れる仕組みです。私は強引に入所したいとは言いたくないですね。自分たちで作った施設なので、思い入れもありますし、いいところだとは思いますが、皆にとって平等な場所であって欲しいのです。
私は2007年に「終末期医療を考える会」に加入しています。その会の雛形をもとに終末期医療に関する希望を書面にしていて、何度か書き直しています。延命治療はしたくない、訳がわからない状態になったら早目に眠らせてほしいというのは当初からの願いで、夫を看取った後で、体幹拘束はしないで欲しいというのを書き加えました。長男、長女のサインももらっています。自分で意思を表明できなくなった時のために書面にしていますが、死ぬ前には意見が変わることもあるかも知れませんね。

ご自身が亡くなった後のこともお考えですか?
この家の場所と隣地は私と弟のものなんですが、土地の条件で別々に売ることができないようなんです。私たちの子どもの代で争続が起きて欲しくないから、弟とはどちらかが死んだら、まとめて土地を売ってお金に換えておこうと話しています。いまは有料老人ホームに入っている弟が先だったら、私はここの家に執着しないで、施設に入ろうと思っています。
夫の眠るお墓は、夫の父の代からのもので、夫の家族がたくさん眠っています。私が会ったことのない方々もいらっしゃって、そこに「初めまして、周子と申します」と言いながら入っていくのだと、笑い話にしています。
河さんにとって、老いとはどういうものですか?
90歳のある日、区からのお知らせなどいろんな書類がたくさん届いた時に、読んでも理解できず、とてもショックを受けました。文字が読めなくなって、こんなこともわからなくなって、これからどうなってしまうのだろうと、とても不安になってしまったのです。それで気分が落ち込んでしまい、何もできなくなりました。どんよりと過ごしていた時に、うつ病の既往のある姪が電話をくれて、30分くらい、うんうんと、何も言わずにただ私の話を聞いてくれたんです。最後に「おばさん、自分に厳しすぎない?おばさん、もうその年なのよ」と言われて、ハッと気づきました。そうよね、90歳をすぎているんだもの、しょうがないんだと思って、そこから1ヶ月くらいかけて這い上がりました。
それからは、うつ病や認知症のひとがいる家族には「自分がどうなるのかわからなくて心配なのよ。黙って話を聞いてあげて」と助言しています。ひとと話をすること、聞いてもらうことはとても大事ですね。
その後、この数年の間に50年来の2人の友人– 1人は白川さんです–が亡くなった時にもとても落ち込みましたが、ケアマネジャーさんたちに支えてもらって、いまの私があります。不安と緊張の薬はたまに飲んでいます。
気が滅入っていた時に「人生で楽しかったことを100個書き出しなさい」と誰かに言われて書いてみたのですが、20個くらいで筆が止まってしまいました。書き出した20個くらいの中でどれが一番かと言われると、それもわかりませんね。
私は元来能天気な方だと思います。「あるがまま」が口癖で、小さな波風はあるものの、95年間どん底まで落ちたことはありません。最近は、無くし物があってもあまり気にしないようにしています。そのうちどこかから出てくるでしょと思っていたら、10日くらい経って、思わぬところから見つかります。何かやっている最中に中断して他ごとをやると、忘れて置いたままになっているんです。
「杉並・老後をよくする会」や「終末期医療を考える会」に所属して、40代からずっと歳をとることに向き合ってきたつもりです。死ぬのは怖くないけれど、やっぱり自分のことができなくなってひとに頼らなければいけなくなるのは嫌だし、明日の私がどうなるのかは不安なんです。人生って、そういうものなんですね。

エピローグ
インタビューから1ヶ月後に、河さんはご友人と温泉旅行に行きました。旅館で夜、ベッドの間を横歩きで移動している時に躓いて転倒してしまい、歩けなくなってしまいました。ご友人から当院へご連絡をいただき、骨折が疑われる状況であったため、画像検査や入院治療ができる病院を受診してもらうことになりました。旅館の車椅子を借り、ご友人に車椅子を押してもらって東京に戻りました。診断は恥骨骨折で、河さんはそれから約1ヶ月入院し、リハビリを行なって、少し歩けるようになって退院しました。家に帰ってからも一生懸命にリハビリを続け、骨折受傷から4ヶ月経ったいまでは、受傷前とほとんど変わらないくらい動けるようになっています。
編集:児玉紘一
執筆・文責:むすび在宅クリニック院長 香西友佳
対談日:2025年某月